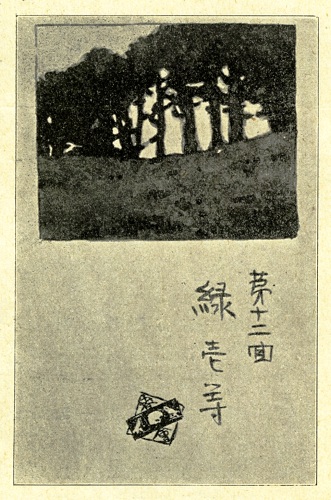スケッチブック
K.S.K.
『みづゑ』第一 P.15
明治38年7月1日
△某先生門下の秀才連が、ある年五六人連れで寫主旅行に出掛け、諸所を寫し廻つて、終に箱根へと出て來たが、銘々風雨に曝されて、みすぼらしい體裁でありながら、よせばよいのに福住へと泊り込んだ。さて翌朝出發といふので、大勢の女中達に送られて、玄關へ出て見たら、歯の欠けた泥まみれのや、鼻緒の抜そうなのや、前のめり、後べり、ひき汐に河岸へ取殘されたやうな下駄や、護膜が切れたり、爪先が破れたり、底の剥がれた、掃溜めにころがつてゐそうな靴が、磨きたてた沓脱石の上にずらりと並んでゐたのには、さすがに鐵面皮な連中も、女共の手前脇の下に冷汗を催したそうな。
△この連中が東京へ着いた時、新橋で別れて各々宅へと俥を急がせた、さてそのうちの一人は腹が減つて堪らなくなったが、懐中にあるものは宿屋の書付ばかり、いよいよ窮して東夫に立替させ、途中のそばやで一時凌ぎをやらかしたといふ。
△矢張りこの人達の話だか、宿屋の女中が、お湯があきましかたら御召しなさいといふて來たので、自分の連れはもう出たのかと、早速風呂塲へかけつけ、いでやと桶の蓋をとつたら、ワーッと中から飛出すものがあるので、氣絶しない許りに驚いたが、これは連れの男を嚇すために、風呂の蓋をしてうんうん言ひながら待つてゐたのだといふが、さてさて苦しい洒落をしたものさ。
△田舍で寫生してゐて一番困るのは、肥料桶を擔いた百姓がしかも風上に立て見てゐられる時だ。あゝ早く往てくれゝばよいと思つてゐるのに、この間來た繪かきはあの森を寫したの、あの橋の向ふにはこゝよりももつとよい景色があるのと、呑氣に話しかけて中々去りそうにもしない。見れば桶に一ぱいになってゐるのに、さぞ自分でも重からうと、却てこちらから同情する次第さ。
△後に立て繪を見る人のうちには、黙つてゐるのもあり、又大に饒舌るのもある。頬冠りをとつて「御苦勞さま」と叮嚀に挨拶するのは田舍で、「こいつは一寸見られる」なんて小聲で言つてゆくのは東京の生意氣連。