ちゝぶ日記
大下藤次郎オオシタトウジロウ(1870-1911) 作者一覧へ
汀鶯生
『みづゑ』第三 P.11-13
明治38年9月3日
葉月十一日はれ、昨日見し瀧寫さんと思ひて六時頃山を辭す。鳥居をはなれ下りゆくに傾斜急にして靴にてのあゆびいと便なし。ある時は走りて木の幹に身を投げかけ、ある時は傘を力に足を横さまにして下る。疲れ甚しく汗とめ度叛く流れぬ。漸くにして瀧ある處に到るに、谷深ければ日に未ださゝず、わたり小闇く水の音しめやかに物淋しさたとへがたし。長き橋の中程に三脚据えて寫生を試みしが、槲の落葉の風に音するをも、大蛇など出でしにやと怪しまれて心おち居ず。山の小僧の、さきつ頃日暮れて歸る時、このほとりより山狗につけられ終に頂上迄去らざりしよし、昨夜きゝし話も思ひ出されて、心弱しと自ら嘲けりつゝもなほ四方の見らるゝ心地すなり。さらぬも汗になりし身の、この朝凉に冷え渡りて自からうち慄はるゝに、久しく居るに耐えで、瀧は只其趣を模せしのみにて筆を收めぬ。
これよりは急ぎ山を下り、荒川の岸におり立ちて大岩小岩の水と戦ふさまを寫す。前面青緑の山屏風を建てし如く壓して、空なく遠景なく作畫尤も困難を覺えぬ。
繪成りて後橋の傍の茶店に入りて休む。したゝかに茶を飲み菓子な貪りて、さてうち立んとて懐さぐるに細き錢なし。剰錢ありやと問へば無しといふ、やうやうにかき集めて菓子の代丈け調へしが、茶の料さし置かで去りゆく心若しさ、河原の寫生にも増して耐えがたかりき。
暑く苦しき山路幾里、畫過る頃贅川の角六に着きぬ。程なく烈しき夕立のありて、樹々の緑は洗はれて美はしく、かの見晴しよき部屋には隅々迄も凉氣滿ちて今朝の疲勞を忘れしめたりき。

十二日晴、寫生すべく出たゝん勇氣もなければ、坐敷に在て前に見ゆる大景を寫す。四五時間にして漸く成れり。此わたり折からの盆休みとて近き家々の小娘五六來りぬ、何れも今日を晴れと粧ひて罪なきことども語り合ふ。菓子など求めて碩ち與へ、くさぐさの事問ふに、たゞうろへみて答へぬもあり、さし出でゝ語るもあり、とりどりに愛らし。その中にやゝ年たけてはあれど、勝れておちつきありて、語る事もいやしからず、床しきふし多き少女あるに、この地の名ある人の娘にもやと思ひて、宿の人に問へば、たゞの農夫の娘なれと、父なる人は村に珍らしくも學問ある男にて、庭の教へも常日頃よく行届きおれりといふ。實に氏よりも育ちといふは尤もなりとうなづかれぬ。
十二日はれ、足痛みてあゆみ難ければ、俥雇はんとするに此地には無しといふ。折々大宮より上り來る歸り俥ありといふに、待てども今日は來らず。此家の勝手元の有樣など寫して永き日を暮しつ今日も前山雲たちて雷鳴すさまじく、折々雨ありていと涼し。
十四日くもり、漸く俥來りて大宮へゆく。角屋に着きし時は四時を過ぎたり。さきの坐敷の先客あればとて二階なる一室に通されぬ。
十五日晴、武甲山寫さんとて秩父紳社のほとりにゆきしが位置あしく、割愛して小鹿野街道なる荒川の岸にて、汗ぬぐひつゝ一枚を寫す。繪の出來あしかりしも、暑さに苦しみし紀念としてはまた棄て難かり。
流行病視察のためとか、浦和よりあまたの警官來りしものから、室不足を告げて我れは前に居りし新坐敷の客と間を共にする事となりぬ。さて相客はと見れば、鼻下に髯蓄へし四十あまりの尊大なる男にて、わたりに白紙筆洗など散らばり居るを見れば、遊歴の畫師にもや、我れを同し角の稼するものと恕ひくか、突然口を開きて、此地には見込なけれは御忠告申さんと思ひし、自分も今度は失敗せり、一枚の畫に謝義は何程より持來らずなど問はぬ事迄かたり、猶いくたの自慢話の後、三峰にては自分のあとより此近くの畫工の上り來りし事、自分には揮毫を乞ふもの頻りなりしも彼には其事なかりし事此畫工に初めて面會せしとき、彼は名刺を持來りしか自分は與へさりし事自己の宿所も言はずして、こなたの宿所を問ひしかば、其無禮を貢めし事などくだくだしく語りぬ。我も初めは彼の名を問はんと思ひしが、これ等の話をきゝてその人柄をも解し得たれば、終に問はずして止みぬ。
十六日曇、おりおり雨あり。今朝は、畫師の昨日に引かへ馴れ馴れしく語りて、自分はこゝ住めは序もあらば立よられたしとて彼より名刺出しぬ。三峰にてありしといへる事とも思ひ出られていとおかし。
七時頃關氏來りて、山に霧深けれどいつ迄も滞留の身にもあるまじければ、近き名所を案内せんといはる。一冊のスケッチブック手にして關氏に從ひゆく事約一里、琴平山に出つ。石級登る事二丁餘、拝殿あり。更に三四丁にして奥の社に達す。銅にて作りし神像立てり。山を傳ひてゆく事數町、二十六番の觀音堂あり。危岩の間に建てられし丹色の殿堂、欄朽ちて納札の跡まだらに、楓樹影くらく苔滑らかに幽邃を極め、武甲山前に聳えて秋の色を忍ばしむ。山を下りて本道をゆく事十餘町、左に折るれば二十八番の觀音堂あり。堂は直立二百餘尺といふ白色の大岩の下にありて、面白き位置をなせり。有名なる秩父の鐘乳洞はこゝにあり。入ロと出ロと離れて二つあるは、吾國に比なしと里人誇りぬ。案内者を頼み燭を燈して入る。狭き口を身をかゞめて進むに階子あり、七八級を下れば外部の光り全く遮られて、たゞ一穂の燈のみ覺束なく照せり。こゝは疊十ひらを敷き得べき廣さにて、鐘乳石、石筍等あまたあり。案内の男竹竿の先に燭を結びて高くかざしつゝ是は何、彼は何と形の似たるを佛の名として事々しく述べ立づ。更に階子を下る事數十階、或は廣く或は狭き洞穴の間を縫ふて、上り又下りとかくして出ロに達す。出口は入口の反對の側山上に在り、初めてなればいと珍らしと思ひぬ。
他に見るべきものもなければと、元來し道を大宮へと歸りしが、途すがら小流あり橋あり水車ありて景色あしからず、秋にもならば再び遊ばんの心も起りぬ。
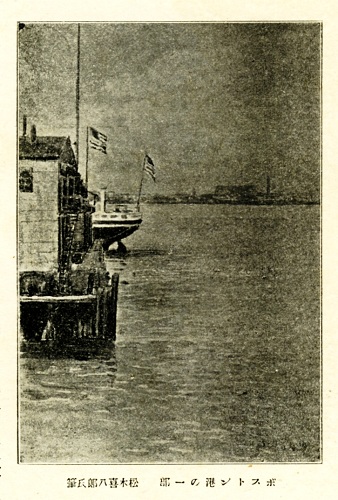
十七日曇、今日は都へ歸らんと思へは、とく起き出で仕度す。六時馬車に乘る。かの畫師も共にと、車の上にて携えし毛布敷きて我に半座を頒つ。ゆられゆられて太駄に到り馬を代ふ。こゝに四人のホーカイ節あり、乘合の人々興に乘じて小錢を擲つ。かの畫師いつこよりか梨を求め來りて我にも頒つ、重ね重ね殊勝なる振數とやいはまし。
車の本庄に着きし時、上野行の列車の動き始めぬ。一汽車おくれて宿に歸りしは、夕陽小西湖に赤く輝く頃なりき。(終)
