日本と水彩畫(一)
丸山晩霞マルヤマバンカ(1867-1942) 作者一覧へ
丸山晩霞
『みづゑ』第七 P.5-6
明治39年1月3日
前號の豫告に大氣焔の文字があるがそれは聊か不穩の感がある。余は單に自分の意見を述ぶるに過ぎないのである。余は今本題を論ずる前に余のこの度斯界に現れ、尤も誠實に、斯道の發展を計らんと决心したる動機を、述べやうと思ふ。讀者よ、暫く我が出樂園の記より見よ。
出樂園。余が愛つる樂園は故郷である、余が放郷を愛慕するの情は世の常ならざりき、無二の樂土永久の生涯は、この幽靜なる境より、他に移さじと决した、この决心ばかりは今日まで迷はなかつた然して、余の熱閙雜踏の都會を嫌ふの情も、又尋常ならざりし。以前書生時代、その無邪氣なる時にすら、都會生活を嫌ふの情は、今と變らなかつた。故郷の風景は我が意に適し、故郷の人情も我が意に適して、彼等は彼等の住む茅屋の如く、至て素撲であるが、茅屋の中に充てる温暖は、又彼等も持つて居る。無量なる温和の愛の霑ひに、我もも人も浴しておる。訪問と來客。如何ばかり誠實を以て送迎するのであらう、主客の上に些々の拘束なく、待遇振りの手厚さ心切さ、快樂のあらん限りを盡さしめ、天眞の滴りは清水の如く溢れておる、彼等の小天地なる郷には、世界の望みもこもりておる、こゝが世界であると滿足して、他を顧みない。ほゝ笑む愛のめぐみに慰め、海見ぬ生涯を决して恨まず只年々の凶豐作に眉顰むる彼等こそ、實に神の愛で兒である。このやうな趣味津々たる田園の生活を、なすべく更に决行の觀念を高めたは、過ぎし我が在歐の時であつた。麗しくして閑雅なる英國の田園、或は幽靜なる佛國の田舍、それに學べる田園畫家の生涯。彼等は活々としたる大自然の美に浴しつゝ、日々を送る穩靜の生涯は、如何に余の同情を促かさしめしぞ、それと同時に余は理想の隠れ家を故郷に建てた。その隠れ家は歸朝と共に實現した。そして理想に近き生涯を五年送つた。欧米の畫堂を經めぐり、或は水彩畫家を訪問し、ありとあらゆる水彩畫の研究。それより得たる智識は决して少くない。歸朝後の五ケ年も、全く水彩研究であつた。おさなあゝ故郷の風物。譬ば我が幼稚馴みの親しき友のやうである、交れば交る程親しく。我の幼稚時代には、彼も幼稚であつた。
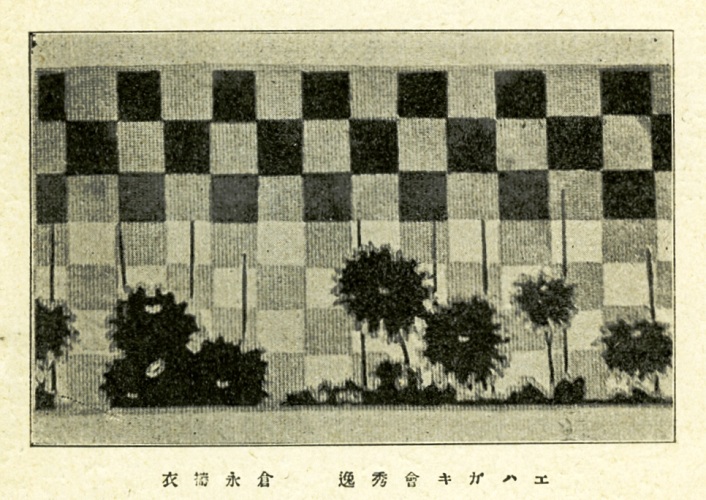
今のやゝ勝れし眼を以て接すれは、彼れもやゝ勝れたる趣きを小すのである。彼の深秘なる胸奥を見出すは、甚た至難であるが。彼は打ち解けて、共の深秘をも物語りそふである。我も愛撫し彼も愛撫して、今では離れ難なの交を結んだのである。されど今は別離の止むなき運命となつた。それには種々なる動機があるが、先づその重なるものは樂園の故郷には、自然の外語る友なき事。平和となつた今日。斯道の爲めに活動し、大に其の發展を計る事、之れ等が余をして樂園を捨てゝ、都に出でしめた動機である。大下氏は余の親友、しかも同し流れを汲める人。是よりは共同一致斯道の爲めに献身的に盡さんかな。
いざやこれより本題の意を述べん。
目本と水彩畫。水彩畫は文字の如く諸君の既に知つて居らるゝので別に説明するの要はない。等しく彩畫であるが、水彩と云ひ油繪といふも繪畫の目的からは、何れも仝一であるか、油繪は水彩畫に比して、着彩其の他に多少の相異があるから、これを説明しやう。油繪は、油を以て繪具を製し、丁度漆のやうな牲質のものとし、これを強き毛の筆に着けて、布、板類、厚紙、壁等に、厚く塗付けて描くのである。其着彩に光耀があつて、寫實といふ點より見れば、水彩は遠く及ばぬのである。出來あがつた畫の上で、水彩は比較的淡泊で、油繪は至つて濃厚である。譬へば、水彩畫は白梅の中で鶯を聞くやうて、油繪は深紅の牡丹の中で、燕の囀りを聞くかのやうである。然し余は决して、油繪を排斥する譯ではない。余は寧ろ日本の凡てが歐米の如く開けて、濃厚なる油繪も、白梅の呑に浴するやうな感を以て、迎へらるゝ樣になる事を、望むのてあるが、然し今の日本の多くは、濃厚なる油繪を迎ふる感念が至て乏しく。却て瀟洒なる水彩畫を迎ふるものが多い、それは何故であるか。先づ一と口に言へば、日本人の氣質が濃厚でなくて、至て瀟洒で淡泊であるからであらふ。日本人の淡泊なるものを愛するは、水彩畫ばかりではない、飮食物から、庭園住家をはじめ音樂、詩歌園藝の類迄、瀟洒にして淡泊なる處に趣味を持つて居る。之れ等が西洋畫の本原なる歐米と異る處で、彼等の萬事が凡て濃厚的である。それ故繪畫迄濃厚的となつたのであらふ。日本人の淡泊なる氣質は、如何なるものか作つたであらふか、之れは實に研究すべき問題である。凡ての力面に渉りて研究するは、中々至難の事ではあるが慨言すれば、余は日本の自然と宗教及び儒教といふものゝ感化をうけて作られたのであると思ふ。猶次號に於て少しく説で見やう。
尚讀者に一言す。水彩に關する記事はこの説の續かん限り各號自分の意見を述ぶる筈である多き讀者にありて。意見を異にし、又は質問の點あらは、遠慮なく申送られたく。そは余の切に望む所である。
