Powell氏の水繪に就て
三宅克己ミヤケコッキ(1874-1954) 作者一覧へ
三宅克己
『みづゑ』第七
明治39年1月3日
亞米利加紐育のホワイトスター會社の、ブリタニックと云ふ巨船に乘つて、ホドソン河口を出帆爲たのは、恰度今から八年前のことでありますが、自分は一生の間にこの時程得意なことは又と無からうと思ひます。彼の有名なブロークリンの釣橋を後に殘して、自由の銅像を見送りながら、渺々たる太西洋に乘出した時は、もう自分は一國の帝王にでも爲つた樣に思ひました。豫て萬國地圖を擴げて、朱や青の線を無闇に引た所謂アトランチツク、オーションとは、自分が今走つて居るこの海かと思ふと、世界も自分の掌中にまるめ込むことが出來る樣で、巳程世界に豪いさうして大きい者は無からうと云ふ念がもう火の樣に燃へて居ました。
とは云ふものゝ自分は最下等船客の一人で、その哀な姿は自分以上に誰も見出すことは出來ませむでした。下等船客數百名の裡、亞細亞人は唯の自分一人でありました。右を向ても左を見ても、屯庫の變つた異人ばかり、愈々薄暗い船室に案内された時は、有繋に好い心持は爲ませむでした。さあその内に船は段々と沖合に出ましたが、さしもの巨船も何うやら揺ぎ出しました。帆綱を吹晒す風の音、エンヂンやプロペラーの響は船の動揺と共に次第に烈しくなりました。元來船には極めて弱い自分、もう全く閉口爲て地圖の上で想像爲たアトランチツク、オーションなるものゝ、實際とは甚だその趣向を異にして居ることを悟り、一國の帝王も今は船底にペッタリと倒れて、青ざめた死人同樣に爲つて仕舞ました。
ホドソン河口を出て九日間は全くの病人で、クラッカーとコーヒの外は何も口に入れなかつたのでも、如何に弱つたかゞ解るでありましやう。

二日日の夕刻から波は愈々高く、船は益々揺れ始めました。そうして時々甲板に打上る大波は、恐ろしき凄き響を爲て總ての物を洗ひ去つて行くやうです。自分はこの響を耳にするのみでも、最早何うしても立つ元氣は無い。親切なボーイはパンとビーフテツキの一片を態々持て來て呉れました。然し白分はノーサンキユと斷るのが勢一杯でありました。時に傍に居つた者不思議な顔して、日本人は米の外には何も食はぬと見へると、少しく冷笑の風がありましたが、如何にせむ最早全くアトランチックの波濤に閉口爲て仕舞ふたのでありました。處が或日のことべツドを列べたアイルランドの大工の爺の助で、思切つて甲板に上つて見ました。きうして掌中に握り潰すことが出來ると思ふたアトランチックの大波を實際に見ました。空は一面の灰色で水の色は深き藍色で、その凄きことはバシフヰツクの夫れとは大に趣向を異にして居ります。この一場の活畫は自分が大西洋を航海した、唯一の紀念物でありました、假令自分は青菜の萎れた樣に哀れはかない有樣でありましたが、今このすさまじき大洋を航海爲しつゝあることを思へば、さすがに勇壯なる感の湧き來るを覺えたのでありました。
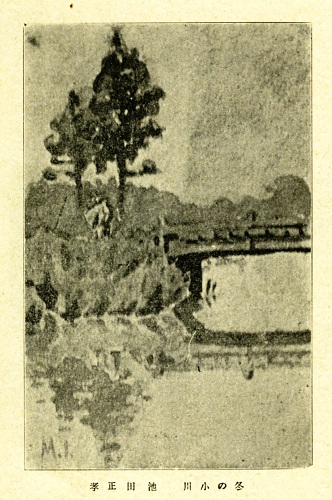
指折り數へて待つて居つた九日目の朝は、終に來てもう今にリバプールが見へると云ふ騒ぎになりました。自分もこの時は元氣付て顏も洗ひ、髪もブラツシで掻き揃えて、一番新しきホワイトシヤツ着て澄し返つたものでした。
リバプールから倫敦までは約二百哩、僅に四時間餘の直行で先づ無事倫敦に着きました。着た翌日自分は直にナシヨナルギヤラリーを見物爲て、その足で又直にサウスケンシントン美術館に行きました。この美術館には特に英國水彩畫の歴史的コレクションがあって、先づ自分には此上も無い研究場でありました。今こゝに此畫堂の樣子をお話爲ると餘り長引から、これは更めて他日と爲ますが、兎に角に新古幾多の畫家の作畫が秩序正しく列むで居ります。自分は恰度飢へた狼が食を漁る樣に、一々と作畫を見物して居りましたが、現代作家の製作中に最も強く自分を刺激爲たものがありました。抑もそれが大下君の所謂『御馴染のポーエル氏の海の圖』であります。自分はこの畫に對しては、技術以外に或る特別の感激を受けたのです、即ち彼の凄きをそろしき大西洋の波浪を聯想爲たのでありました。勿論その聯想を自分に與へた力は、確に巧妙なる技術の結果に外ならぬ譯であつて、筆者その人の披巧に敬服爲すべきは敢て論ずる迄も無いことでありますか、議論はさて措き白分は眞實其海景に感心致しました。空が一面の灰色で、インヂゴの海原に白き波が立つて居つて、島も無ければ船も見え無い。唯鴎の二三羽が波間を飛び行くのみてありますが、恰度自分が甞て見た彼の大西洋の波の景色と彷彿たるものがあります。さうして見て居る内に、風の音や波の船端に打突る響が耳に響く樣な氣が爲て、一幅の水彩畫は端無くも再び自分を恐ろしき凄き大西洋に伴れて行つたのでありました。
筆者その人の名はSirFrancisPowell.と云ふて、スコツトランドに住むで居る水彩畫家なのであります。當時尚存命でスコットランド水彩協會の會頭であつたのです。そこで自分は稽古ながら且つ又他日の紀念にもと、是非共模寫を爲やうと云ふ考を起し、早速美術館の事務所に行き至つて無覺束い英語で其旨を述べました、處が案外容易に承知爲て呉れまして、一週間に二回通學することゝなりました。然るにこゝに面倒なのは、ポーエル先生は當時末だ存命の畫家であるから、模寫希望者は一々畫伯の承諾を受けねば、手を下す譯に行きませぬ。そこで自分は恐る恐るポーエル先生に其旨を通じました。愈々手紙が書けていざポストに入れる時に、果してこれがポーエル先生の手許に届くであらうかと、マー一寸夢の樣な氣がしました、すると二日目に返事が來ました。これは承諾の旨を書たもので、其時の自分の悦は何とも譬樣も無い位であ嚇ました。そこで直に其手紙を持參して美術館に行き、こゝに公の許可を得て愈々模寫することゝなりました。
處がこのポーヱル先生の波の圖と云ふのが、非常な精密な繪であつて、一寸模寫と云ふ譯に行きませぬ。夫れには波の微細な形が一々と丁寧に畫てあるので、イザ模寫と云ふ段に至つて、もう何うしても手の附け樣が無いのでず。但し見れば見る程益々感服するのみで、種々に工夫して終にその模寫を仕上ました。勿論これは技術研究の爲にもなりましたが、然し一には大西洋航海の紀念として、尚又一つには倫敦到着後のFirstinfluen-ce.としてこゝにこの紀念物を得たのでありました。さうして自分は洋行土産の一つとして、この模寫畫を今に火切に珍重爲て居るのです。原圖は即ちAGreyDayatSeaと題するのでありまして、尺に尺四五寸の小幅であります。勿論この繪を以て館中唯一の名作とは云ひませぬ。又ポーエル先生が英國水彩界に於て、果して絶代の名家であるか何うか、これも固より知り得る處ではありませぬ。唯然し白分に對して一禰不恩儀な感想を與へしめ、端無くもブリタニック甲板上の光景を聯想せしめたことは即ち事實で、少なくとも自分一人に取りては終生忘るゝことの出來無い繪なのでありす。
然るに斯も因縁ある繪が、曩には一度大下氏の手に依りて水彩畫栞の卷頭に掲げられ、今又本誌の口繪としてこゝに再びこれを相見るのは、自分に取り如何でか一片の感無くして止みましやうか。ポーヱル先生の海の繪に就ては、實にこれだけの因縁があります。
然るにこの繪が屡々諸君の御目に入るのは、自分に取りてこの上も無い悦であります。
されば自分は今こゝに大下氏が熱心縮寫製版の煩勞を執られたるを謝すると共に自分が滿腔の喜悦を以て讀者諸君と共にこの口繪を迎へたいのであります。(終)
