山菅日記
大下藤次郎オオシタトウジロウ(1870-1911) 作者一覧へ
汀鶯
『みづゑ』第十三 P.7-15
明治39年6月3日
朝八時目白發の汽車に乘る、林の緑いろ深き中、さては稍々黄みたる麥畑の間を過ぎ、さしてゆく日光の山々を車窓の左に眺めつゝ十二時過宇都宮につく、爰に車を換へてゆくに、家あるほとりには必ず麻の畑ありて、その若葉のうす緑に日に照らされたるも美しく、野の面には燃ゆらんが如く紅に咲出たる山躑躅の花もいとあざまし、やがて濃き翠の杉の森、雄々しく立てる赤薙の山も漸く口に親しみ來り、かくて二時半といふに車は日光停車場にはてぬ。
花袋氏の紹介を得て宿を南谷の照尊院と定めつ、山寺の晝も靜かなる、番僧は睡りをや貧ぼる訪へど答ふるものなし。こゝは寺とはいへど墓地なく、日光十六院中の高き格式ある大なる堂舍なり。傍の庭園を見れば。築山泉水の配置よきに藤あり燕子花ありて、初夏の眺あしからず。暫時にして二三の雛僧の庫裏より出來りて奥なる書院に導き、火桶を運び茶をすゝめなどす、態とならぬもてなしの嬉しく、この旅幸多かりと心に思ひぬ。
繪にすべき處をさぐらんとて、寺門をいで大谷川に沿ふて上る。五月の末は新緑のいと美しき頃なりときゝしが、そは半月程前なるよしにて今は都の梢の色と少しも異ならず。橋を渡りて願滿に到り見るに、途々山吹の花の黄なる、藤の紫と交はりて目にうるさき迄咲きみてり、川の水逼りて淵をなせるほとり、老樹の若葉日にてりて水に映じ、さすがに捨てがたき眺めなれど、茶を賣る男の近づき來りて、要なき口上立に興を殺がれつ、道なき迄上流を極めてやがて寺へ歸りぬ。
灯つきて後階上に主僧と夕飯を共にす。天台宗にて、叡山と當所は戒律固くして一切肉食せぬといふ、食膳の富は元より願はぬ事なりしも、只困じたるは主僧にさゝれし酒盃にて花袋氏は數盞を辭せられぬ由なれど、我はたゞ一杯を傾けしのみにて耐えがたき思ひありき。
五月二十三日半晴
老鶯の頻りに啼くに夢を破られ目を開けば、雨戸さゝぬ紙障に朝日のかげまばゆし。遲かりしと起き出で庭を流るゝ清水に口清め顔洗ひて、さて小山に登りて見れば、大谷の流れは川霧たち籠めて、近きわたりも物の形定かならず、北の方黒髪山は白雲むら立ちて、巓き迄も掩はんとするさまなり。今日は湯元迄登らんと思ふ身の後の空こそ氣遺はしけれ。
景色寫すになくてならぬ限りの、さゝやかなる荷物片手に足尾に通へる馬車の線路に沿ふてゆく。清瀧より右に九時の頃馬返しに着き蔦屋に憩ふ、主婦も茶を運ぶ少女も見知れる人々なり水の色いよいよ蒼く、石の形ますます大きうなりゆく女人堂のほとりにて溪流にわかれ、方等般若の瀧を右に、登り登りて大平を過ぐれば左に華巖の瀧道あり、下る事數町、小さやかなる茶店ありて老翁たゞ一人客をまてり。樹枝に手を加えて見上見下す巨瀑七十五丈、實に關東有數の壯觀なるべし。四方の山々新緑の賑はしき間々を八汐の花の彩りて、見渡す限り黄に緑に青に樺に、まゝうす紅なるさへ交はりて、秋の美しさもこれには過じとこそ覺ゆれ。
更に元の道を登りてゆけは、程なく鏡の如き中禪寺の湖畔に達す。八重の櫻の、雪の如く廣前に散り布きたる中官祠に詣で、湖を左に岸をめぐりていつしか菖蒲ヶ濱も過ぎ、地獄茶屋に黴臭き菓子を味ひ、龍頭の瀧を後にして、やがて戰場ヶ原にさしかゝるに折柄大空一面に曇りて折々小雨さへ降り出たり、我右の方には男體山雲に連りてたち、前面は湯嶽金精ヶ嶽、さては雪を頂く白根の山々天を摩して聳え、限り知られぬ枯野をはるかに、湯の瀧の一點白く懸かれるを見るべく、落葉松の林遠く走りて展望極めて壯大に、雲いよいよ低く彌が上に重りて晝なほ暗きに、程近きあたりに雉子のほろほろと鳴くなどいと物凄く、一人旅の影淋しき身には、ことごとにうち驚うかるゝなりき。かくて夏はあやめ草生ふるとかきく沼のほとりも過ぎ、落葉松の林も盡きて二三の家ある處より、左に入りて湯の瀧を見る、こゝは華嚴のそれとは趣を異にして、懸崖直下の態なく稍勢を欠けど、瀧壺の近く迄ゆきて見上るを得るため却て壯大を感ずるなりき。瀧の傍の細徑を上れば湯の平にて、蒼く山影を浸せる湖は吾眼前にあり、山深ければにや四境幽邃にして自ら心も澄みゆく心地す。熊笹茂れる小山に連りて樅檜等の森林あり、斧入らぬ山の幾千年をか過つる、巨木の湖に半ば埋れ朽ちたるなど、思ふに太古より其儘なりしなるべし。水に沿ふてゆくに兎島といへるあり、小暗き常磐木の中に、一本の山櫻の僅に綻びそめたる、再び淺き春に逢ひしは嬉しかりき。初袷の袂輕かりし日光の町より僅に六里、こゝは猶冬の儘にて、熊笹の果しなく黄なる、黒き迄青き樹々の梢を越して、近く殘雪の殊更めきて白き、實に此奥は夏來らぬ里なるべし。深緑に澄める湖水の、漸く白く濁れると共に、硫黄の匂ひの鼻を衝くに、岩角一つ廻れば湯本の温泉宿前に現はれぬ。
吉見屋といへるに草鞋をときしは午後二時なりき階上の美はしき座敷は我がために清められ、床の瓶には赤き石楠花あまた挿れたり。此町の人々冬は日光へ歸るが例にてこゝに來りしも僅か十日程以前なりしとか、されば浴客も稀に物靜にして我が心にかなへり。六里の山道足の疲れも心地よき温泉に愈せられて元氣も回復し、友への繪葉書など描きて日を暮しつ。
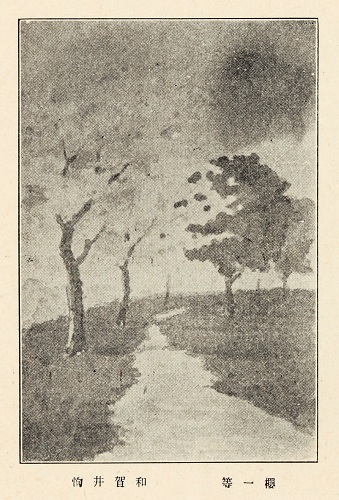
五月二十四日雨より晴
軒端を傳ふ雨の音に起き出でん心地もせず、朝の程は浴し文よみてくらす。正午の頃より雨おさまり雲晴れしかば、湖邊にいで熊笹の中深くわけ入りて白根の山を寫す。笹は腰にも及び密生して地を見ず、朽ち或は燒けたる巨木の、三々五々立ち續きてうら淋しく、屡々後ろ見せらるゝなり。老鶯雉子など程近く啼き、時には山鳩の友よぶ聲もすなり。
二時三時の後繪は半ば成りぬ。動ける雲光れる雪、暗き林明るき笹原何れも寫すに難きものゝみなり。湯の嶽の麓あたりを探りて一二のスケツチを得薄暮宿へ歸りぬ。
五月二十五日晴
秋に再び遊ばんことを約してこの朝吉見屋をいつ、途に昨日寫せし白根を仕上げ、十時頃この懐かしき湯の湖に別れぬ。來れる時に引かへ、晴れやかなる戰場ケ原もいつしか過ぎ、正午中宮祠に着米屋といへるに晝食をとる。湖中の産なる鱒は膳に上りて味よし。日光の寺に歸りつきしは三時の頃なりき。
五月二十六日晴
瀧尾道に飯盛の杉を寫す。此地杉の巨木多く、街道の並木は有名なるものなれど、瀧尾道のそれも苔蒸し枝茂り、狹き道は傾斜ありて石を疊めるなど、繪にするに適せり。
五月二十七日半晴
瀧の尾の寫生をつぐ。
五月二十八日半晴
瀧の尾の寫生をつぐ。午後より後庭にいで男體山を寫せしが、雲多くして山を掩ひ不成功に終りぬ。
五月二十九日雨
後庭に小池あり、石は苔に埋れ、水黒き中を築山の杜鵑花紅の影を映ぜり、燕子花のゆかりの花雨にぬれて艷に、古りたる石橋の上に折々飛び來る鶺鴒の姿も面白きに、雨の日ぐらしそを寫して一日を送りぬ。
五月三十日雨
後庭の寫生をつぐ、
五月三十一日
後庭の寫生成る。この夜用事なき身の早くより臥床に入りて、靜に降りしきる雨の音をきゝつゝ眠につきしが、夜半ばかりの頃枕元の紙障に只ならぬ物音す、何事ぞと驚きさめて、マツチかきさぐり燈てらし見るに、緑に向へる方の障子骨おれ紙破れたり。雨戸さゝぬ事なれば、何物か來りて内に入らんと試みしなるべし、何となく胸安からぬに、此夜はよくも眠らであかしぬ。
六月一日雨
今日も雨なり、軒の玉水その音にもはや飽きたり、明日は一年にたゞ一度の東照宮の祭典なりといふに人々皆晴を祈れり。晝過る頃より幸に日の光もれぬ。またも雨ありてはと瀧の尾の寫生を繼ぐ、よろづの草木悉く濕ひて前と調子異なり筆つくべく詮も知らず。
六月二日晴
とく起き出でゝ瀧の尾にゆき、五日目にして漸く成る。骨折りし甲斐もなく面白からぬ出來なり。
祭りの行列の東照宮を出るは正午なりときゝしかば、時をはかりてゆき見るに、大鳥居のあたりより御旅所まで、見物の人々居並びたてり、朝陽館前の廣き道には、赤き白き段々染の幕引き廻ぐらし、椅子あまた並べてテントかけたるは、ホテルに宿れる外國人のためなるべし。五重塔近くにゆきてまつに、やがて打ち響く太皷の音と共に、列の先頭ははや門を出でたり。赤き羅紗にて作りし唐樣の兜を頂き、直衣きたる士の手には鉾を持ちたり。其數百人なりといふ。次にやゝ衣の美はしきを着飾り、同じく鉾を捧げたる神官あり。顏には天狗の面をつけたり次は一對の獅子にして、三人の人夫これを支ゆ。次は神女なり額に白き布をつけ、紗の衣地に曳き、手には中啓と鈴とを持てり、其數八人。次は社家の馬に乘れるもの四人、各乘替の馬これに添へり。次には猩々緋の袋したる鐵砲肩にせるもの五十人弓を捧ぐるもの同じく五十人。鎗を立るもの五十人。鎧武者百人。次に頭に花を頂く稚兒十二人。次に末社の神の面をかけし異形の装せしもの五十人。次に御翳といふ軍配團扇めきしもの持ちし四人の男あり。次に太刀負ひし社家一人。御旗負ひし社家一人騎馬にて從ひ。次に五人にて持てる鉾十一本。次に大太皷。次に猿の面を冠りしもの三十人。次に神人六十人。次に伶人二十人、各々樂器を口にして歩みながら奏ず。次に傘持次に鷹匠、各々陶製の鷹を手にす、其數十人。次は床几二臺、金幣、これに次て御本社神輿、多數の人これをかき、又太皷あり。次に左神輿。次に右神輿。最後に諸役人及雨具など持ちしもの數十人隨ふ。一列七八丁に及び奇觀いはん方なし。此行列は御旅所にゆきて東遊びの舞あり。後本社へ歸るなりといふ。
六月三日晴
三枚の水彩畫、結果はあしかりしも得る事多く、名高き祭りも見たれば今は用なき身の、朝の汽車にて都に歸りぬ。
