菱花灣日記[二]
大下藤次郎オオシタトウジロウ(1870-1911) 作者一覧へ
汀鶯
『みづゑ』第二十二
明治40年3月3日
一月二十五日晴、濱邊に徃き見れば、昨日寫しかけし千石船、今朝はその位置を離れて半ば海に入れり。明日は何處の湊に錨を卸すことぞ、先見の明なくして大作に取かゝりしを悔ゆれども及ばす。
二十六日晴、風なく良き日なり、朝寫生箱肩にして北下臺に上る、丘には菜の花そここゝに咲きいて、林には小鳥の囀あり、海は春の如く霞みて浪穩やかに、鷹の島沖の島影長く水に映じて、まこと鏡ヶ浦の稱に背かず、淡紅なる空には富士朧ろに、白帆遠く走り、白鴎近く群れ飛ぶ、いづこともなく耳に入る款乃の聲も長閑に、身は悠々たる自然に化して恍惚の境にある事稍久しかりき。
社頭に三脚据えて松樹を寫す、今日は日曜なれば、里の子達集り來りて賑やかなり。
午後主翁に招かれて茶の間にゆく、茶請は蒸たる甘藷なり。形醜く小に、所謂水芋とよぶものにて、齒に耐ゆるものなし、やゝ腐れのつきしを却て甘味を増すなど主翁のいふに、傍にありし、按摩の、さなりさなりと頻りに追從すなり。主翁曰く、「土に埋め置かざしりしゆへ早く腐れのつきしならん」と、按摩の曰く、「いや何處の家でも腐らしました、お宅なとはよい方です、誰の家は四俵、某の家は十俵、芋は却て埋めぬ方がよいのです」と、又曰く、「此上須賀の芋は格別結構です、八幡船形などは甘味薄くしてとても喰へません」と、主翁曰く、「此芋は八幡から種を取つたのだ」と、按摩こゝに至つて大に狼狽しゴマかして曰く、「されどこの芋は甚だ佳なり、私は他人から欺かれたのです」と、面白き世や。
海邊にいで見る、一人の男の半ば水に入りて長き棒をもち頻りに巖の間を探れるが、やがて其棒を手許へ引けば、大なる黑き蟹は甲を刺れて徒らに鋏を動かすのみ。
夜主翁とかたる、例によつて米國行の話なり、横濵に生れし米國人の子、姉は九歳、弟は七歳なるが、附添人もなくたゞ二人船中に在り、人々怪みて問へば吾等は日本に生れて父母の本國を知らず、這度そを見んが爲めかくは二人して旅路に上れるなりと答ふ、かの國人の勇氣感ずるに耐えたりと。
二十七日昨夜床に就く頃は月光鮮やかに、あけの朝の霜白きを思はせしが、今朝起きいで見れば雨しとしととふれり。つれづれなるもの、實に漁村の雨はその一なるべし、掾近くにたちいでゝそこともなく眺むれば、山は霧にかくれて形おほろに建續く茅屋根は雨に黑みてたち上る煙りもいと力なく、名代きそばの文字ある煤けたる行燈の下に、やれ傘手にしてたてる一人の子守のほか、野には人影もなく、何に驚きてか、けたたましくなく鷄の聲の遠くきこゆると、近き草屋根の下に小麥搗く響のおぼつかなくも耳に入るのみ、いといと詫しき日なり。
新聞もよみ盡したり、小説にも飽きたり、主翁は朝より村の集會にゆきて語るに友なし、怠りがちなりし日記などものする折から羽鳥氏見えぬ。
羽鳥氏の言によれば、この地春夏の候尤もよく、秋の末より春の初め迄は西風いと強くして遊ぶに佳ならず、舊の三月大汐には、鷹の島迄徒歩にて渉り得べく、溜れる水に小魚漁るも興ある遊なりとなり。名物の西風吹く前には、平砂浦鳴りてこの邊に迄も聞ゆることなるが、今日も頻りにその音すれば、明日よりは又風つよからんと頗る有難からぬこと、言ふて歸りぬ。
二十八日晴、昨日は平砂浦鳴れり、今日は果して西風吹き出でぬ。正午頃より勢凄まじく家居も動ぎいでぬ、海のさま如何にと、吹き上ぐる砂に顔を撲たして濱邊にゆき見れば、船は皆島かげに集まりて、高く低く浪にゆられ、濵には海苔拾ふ童も見えず、打よせてはまた打返す激浪は天も衝かん斗りの勢にて馨々聲をなし。岩に衝りては物凄き響と共に、雪崩の如く白浪碎け散りて頗る壯觀を極む。昨は穩やかに今は烈し、さらば明日又平靜の天候ならんも、知れず、あゝ人の身もまた斯の如きか、平穩無事の境遇頼むに足らず喜ぶにたらず、悲慘不遇の境憂ふるに足らず悲むに及ばず、吾は境遇に拘束せらるゝことなく、只目的に向ふて進めば可なり、事の成否は問ふ處にあらざるなり。
狂える風に抗して佇立すること多時、漸く踵を返して家路に向ふに、岡の邊南をうけて暖かなる堤に、圖らず一莖の蒲公英を得たり。大なる天地には大なる美あり、されどこの繊細なる野花にも嚴として奪ふべからざる美を有せり、風に怒れる大洋を見たる眼を移して、この花に及ぼす、吾はその美の輕重を問ふを好まず、床しければ摘みて帽をかざりぬ。
宿の嬰見負はんとて、近く住へるふうちやんと呼ばるゝ小娘をりをり來りぬ、姿焦悴れたれど愼しみ勝にて愛らしき娘なり、吾は今日、この娘の不思議にも米飯と關係ある事を見出しぬ、常は割麥なるを、時々夕飯に米のみを用ゐる事あり、特に吾がためにもやと思ひ居しが、子守娘の來れる時は追焚すべく餘義なくされてかくは白き御飯にありつくなりきあはれ願くはこの娘の日毎に來たれかしと心に念じぬ。
img0727_01.jpg/W.W.Gilehrist,Jr.(水彩)二十九日晴、風つよくして寫生に出でがたし、夕の食事終りて濱邊へゆき見る、昨にもまさりて海荒れたり、それより町へ廻るに、西の空紅に日もまだ暮れきらぬに、道には人影もなく破れし障子に燈火明るく、夕煙前なる山の裾をこめて、高くかゝれる半月のやゝ光りをますの時は、たゞ垣に植えたる篠竹の風に戰ぎてさらさらと音するのみ、實に淋しきは田舍の冬の夕暮ならずや。
夜例の通り主翁とかたる、この地より西方見物の先に一の堂あり、村の若者の集會場なるが、そのあたりの寺の僧も來りて毎夜語り明すを例とせり、さて其ほとりにあしき狸のありて、若者と相撲ひ、忽ち背後に廻りて、襟を捉へ腰に足をかけて人を引倒すため、誰れとて狸に勝つ者なし、和尚若者に敎へていふ綿厚きドテラを帶せずして羽をり、さて狸と立會ふや否、急に其裾を持ちて肩の方に上げよ、かくなさば狸は袋の鼠なるべしと、若者の一人、そは面白し早速試みばやと、かたの如く支度して出ゆきしが、程なく大なる狸を捕えて喜び立歸れり、よくこそと人々賞めたゞへて、四方の戸締を固くし、ドテラを開き見るに、コトコトと音するかと思へば、はや其姿を失ひぬ、戸外に逃出べき透間もなきにと、ある限り尋ねしも更に見えず、こは不思議と和尚も腕こまねき猶そここゝと注意し見るに、此堂に飾れる十三佛の、何やら其數多き樣子なり、彼奴早くも身を變ぜしならんと、數へ見れば十四あり、さてこそと思へど、何れが狸にや形同じければ見分けがたし、和尚即ち曰く、「村人きかれよ、この十三佛は日頃我の信仰厚きゆへ、佛の御前に立ちて咒文を唱ふれば、御佛は忽ち双手を出し給へり、我先づ試みばや」といふに、佛と化けし狸は、こゝぞと和尚の未だ其前にゆかざるに、忽ち双手を突出しぬ。そりやこそ彼奴ぞと、飛かゝりて引捕へ、其夜は早速狸汁をつくりて飽迄喰ひたりといふ。誰人の作り話かしらねど、語る人のいと眞面目なるに、少なからず興を覺えたりき。

三十日晴、北下臺に寫生す、日蔭になれる分の色に苦しむ。
三十一日晴、伊豫ヶ嶽は景色よき處ときゝて、寫生箱携え九時頃出立す、北條を遇ぎ一里程にして本織の村あり、こゝには當國禪寺の本山、里見家の菩提所たる巨刹延命寺あり。やがて瀧田にいたる、山間の淋しき村なれど八犬傳にはその名高し、こゝを過ぎて犬掛より半里、道は二つに分れたり、右は平久里に左は濵に達すべし、伊豫ヶ嶽をと志せしも、一里の上りに苦しむ甲斐あるべくも思はれざれば登山をやめつ、左なる濵の方さして進みぬ、伏姫君の八ッ房と共にありし有名なる富山は道の傍にあり、樹木なく水涸れて趣きなし。時は二時を過ぎぬ、道すがら茶店を見たれど、人多く居て麥飯の包開きがたく、三脚据えて食ふべきよき位置もなくて、こゝ迄携えへしも、今は空腹に耐えで路傍に包みをときしが、人の來る氣配に驚ろかされて半にしてやめぬ。
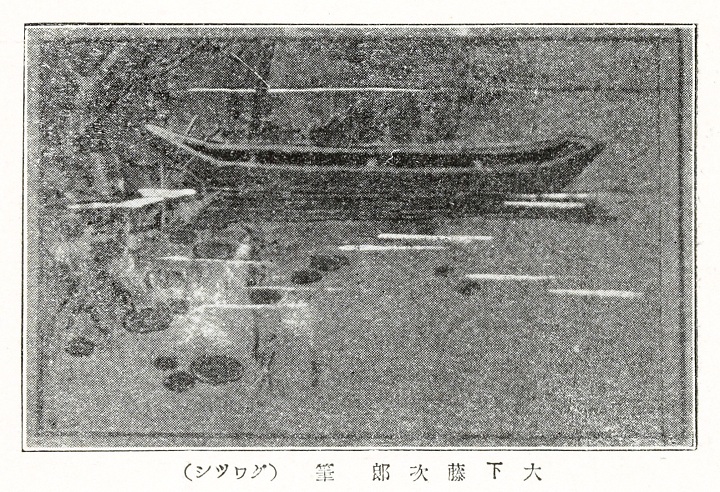
今戸、竹内、市部の村々を過ぎて、加知山に着きしは夕暮に近き頃なり、町并揃ひてやゝ繁昌に、港は狹けれど、風景佳なり明日はそを寫さんものをと思ひつゝ、某屋とよべる三層樓の大なる旅店に宿かりぬ。導かれて表二階の座敷に通るに、障子は立付あしく上の方三寸も空きたり、黑く煤けし紙はいつの世に貼替へしか知らねど破れたるを繕ひもせず、疊は隅々透きて表摺れ座するも快よからず、こは見掛倒しよと悔めと今は詮なし。
食事も終りぬ、風呂はなしといふに早くより臥床に入る、臥具はと見れば、薄き事寄席の布團の如く短かき事嬰兒のそれの如きを一枚敷きて、上にはこれに釣合よき掻巻一つかけたり、硬き木枕に頭いたく、旅は憂きものと思ひぬ。
階下はいと賑なり、客ありとは覺えぬに三味の音喧しく、都々逸端唄の怪しげなるを女中共の互に浮れ合ひて笑ひ興ぜり。
程過ぎて隣室の客歸り來りぬ、年若き男らしきがはや此家に久しく滯留せると覺しく女中共にも訓染あり、何事か心に憤るらしく、床を烈しく踏み、枕もて火鉢の緑を叩き、終には疊の間より湯を流せしと覺しく、下より女中の來りて苦情をいふて爭ふも物騒がしく、吹入る風の戸障子を動かす音、火を警むる町の金棒の響など交々耳に入りて夢に入りがたし、(つゞく)
