穂高山の麓
大下藤次郎オオシタトウジロウ(1870-1911) 作者一覧へ
汀鴎
『みづゑ』第五十二 P.10-22
明治42年7月3日
一
信飛境上四時雪を戴く壹萬余尺の連嶺、人よんでこれを「日本アルプス」といふ。北の方、天に向つて巨匁を擬せる槍ヶ嶽、南、磊々として地に横はる乗鞍、其間に介在せる壮嚴にして而も秀麗なる一峯、これを穗高山といふ。この靈山に對して標高相譲らざる霞澤山あり、その間の溪谷やゝ濶けたる地を上高地とよばれ、山々の雪解の水の絞れて臻まれる一條の清流これを宮川と稱し、梓川となり犀川となり、終に千曲川に合し越後に至りて海に入る。此地人寰を去ること遠く、山水の美は親しく畏友烏水氏より聞き、また雜誌『山岳』によつて夙に知るものから、盛夏の一週日を山中唯一軒の温泉宿に樂しく送らばやと、畫友磯部氏を誘ひて行を共にすることにした。
二
出發は七月十六日、幸ひ快晴であつた。七時十五分飯田町發の列車はやゝ混雜してゐる、淺川以西は初めての地とて、車窓の外は目に新なれば長き旅も飽くことはなかつた、有名なる猿橋も見た、厭はしきトンネル幾個かを過ぎ、やがて甲府も後にして、竜王日野春邊へ來ると、四方は凡ならざる光景を呈して來た。右は金峰の麓より、緩なる斜線を起して西北に八ヶ岳が矗として峙つてゐる、折からの雨後の快晴、飽迄も濃き蒼空を背景として、夏の日に輝ける白雲の大塊團は裾野近く叢立つてゐる。その裾野は私の大好きなコバルトグリーンでベタリと塗られてあつて、處々にインヂゴの雲の影が模樣を織り出してゐる。夏の光に浴した遠き綠の色、それは高嶺の雪の朝日に染まつた時のさまと共に、自然界の色彩のうちで私の最もなつかしく思ふ色である。席を左に移して見る。右の方の晴れ渡れるに引かへて、天日暗く雲霧湧き立ちて定かに山を見ることが出來ぬ、時として車窓を壓するばかり近く其姿を現はすは、音にきく駒、鳳鳳の峻峰であらう、釜無の清瀬は、谷間遙かに白蛇を走らしてゐる。車の漸く進んで小淵澤富士見あたりにゆくと、若木のシラカンバが到る處目につく。
三
上諏訪へ着いたのは午後三時半であつた。まづ牡丹屋に荷を預け、日もまだ高いから湖畔の小丘に上つてスケツチをした。諏訪湖の風景はこゝから見たのでは思つた程よくない、湖畔は青田で、新墾の沼地のやうで少しも趣がない。周圍に樹木が乏しい、湖を廻る山々は低く、其形も平凡で纒りがつかぬ。上諏訪の町も物にならぬ。私の知り合で此地に遊んだ人は、誰とて褒めるものもないが、これ程であらうとは思はなかつた。湖を離れて二三丁、往昔の街道であつたとかいふ並木道は一寸繪になるが、このやうな處は何處でもあるから、態々諏訪迄來るにも及ぶまい。
訪諏の温泉もまた極めて平凡なもので、唯の水が温くなつて地から湧出るに過ぎない。それ故湯治といふと、此邊の人も白骨や平湯迄出掛ける、諏訪の町で他地方の湯花を賣つてゐるのを見てもこの地の温泉の無能が知れやう。
四
十七日は松本行一番列車に乗るつもりで、前晩から宿に其事を通じて、相當の茶代もやつて置たのに拘はらず、朝は湯をかけると白く濁るやうな冷飯を食はした、濁るのも道理か、腐敗して飯の膚には汗をかいてゐる、一番汽車といふても六時近くで格別早いといふのではない、既に吾々の前に東京行の汽車に乗つた人も幾組かあつたのに、當地第一流の旅館で客に腐敗したものを出すとは心得ぬ。諏訪の宿屋も豫て評判はよくないが、景色も惡し人氣も惡しと來ては、湯があつてもスケートが出來ても、終には誰も來てがなくなるのであらう。
汽車の窓から見た朝の湖はさすがに惡くはない、山も霞み水も穩やかで、目に何の刺激もないだけそれだけ美しい。下りて見たのでないから斷定は出來ぬが、上の諏訪よりも下諏訪の方が景色はよいやうである、そして下諏訪よりも岡谷の方が一層よいかとも思はれる。岡谷から天龍川に沿ふて下る、急流を以て名あり、東海道に於て一里餘の河原を有する大河も、この邊では唯の里川に過ぎぬ。
七時五十分松本に着いた、廻りに高い山があり、寫生の材料は豊富と見受けた。町を横切つて島々ゆきの馬車の立場へゆく、馬車は直ぐ出た、馬丁が馬を鞭打つこと烈しく、六里の間絶えず胸を痛めた。
車は梓川を右にして進んでゆく。松本から三里にして波多御料林がある、大なる松林でよい感じのする處である、これを出放れると、梓川の岸近く河原に楊が風情をつくつてゐて、畫架を裾えたい處が澤山ある。梓川に架せし橋のほとりは特によいと見た。
島々着は十一時、直ちに清水屋に入つて、晝食の仕度と上高地迄の荷持人足を頼んだ、人足は中々得られなかつたが、漸く一人さがして來てくれた、これに一切の荷物のほか、こゝで買入れた草鮭やら鑵詰やらを持たせることにした。
五
島々から上高地の温泉宿迄は六里ある、途中の徳本峠は困難てあるし、峠を下つてからは道が惡いから、若し十二時過になつたら島々に一泊しれ方がよいとは、出發前烏水氏から言はれてゐた、時計を見ると一時に間もない、人足の仕度をするのを待たずに、覺束なくも一本の杖を携へて一足先に出立した。
梓川の支流に沿ふて、少しづゝの上りではあるが立派な林道がある。殆ど人に逢はず、また一軒の家もないが、道は迷ふやうな處がない。景色も逼つてゐて至極平凡である。
ゆくこと二里にして人夫は追着いた、早い脚だと驚いてゐる。更に一里にして岩魚返しに着き、堂小屋に休んだ。雪ありと人夫の指す方を見たら、對岸の凹地に泥に汚れた一塊の白を認めた、黄の翅ある越年蝶がヒラヒラ飛ぶ。
それから上下二里の徳本峠である、道はよいが傾斜は中々急で、平均三十度はあらう。傾きかけた夏の日はヂリヂリ照りつける、前にあまり急いたので脚はこの時大分疲れてゐる、杖を頼りに上つてはゆくものゝ、十歩二十歩にして直ぐ休みたくなる、水でもあつて地に腰を下したら最後、再び起き上つて歩行く氣になれない、慾も得もなく、その儘そこに眠つて仕舞ひたい、少し長く休んでゐると、暗くなるといけぬと人夫が催促する、こんな苦しい思ひをして、遠く迄來なくとも、繪を描く處は澤山あるのにと、後悔の念が頻りに起つて來た。呼吸は急しくなる、胸の動氣は烈しくなる、汗は滿身から流れる、目を慰める景色もなく、耳を喜ばす水の音もせぬ、かなり重い荷を脊負ふて、後からついて來る人夫の平氣な顔が小憎らしくも思はれる、それでもいつか知らぬ間に頂上に達した。
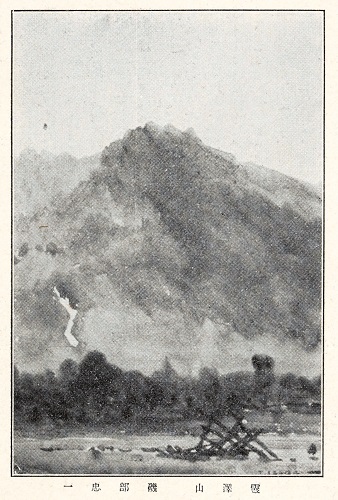
峠といふても八千餘尺の高山であるが、樹木が多くあるため殆ど眺望がない、併し是からは下りだと思ふと幾分か勇氣も出た。日も傾いて來て凉しくもなり、駒鳥の銀鈴のやうな清い啼音も折々は耳に這入る。
峠を下りに向つて數町、忽ち目の前に穗高の全容が現はれた、二三本の栂の大樹が低く目の下に蟠つてゐるのみで、何の眼を遮るものがない、頂上の殘雪は、折からの夕陽をうけて紅に輝いてゐる、そして其蔭はうす紫に染まつてゐる麓の方は夕闇の色もおぼろに、その中のほの白き一線に宮川の河原であらう、何等の壮觀!吾々はたゞ吁!といふたまゝ思はずも立すくんで仕舞つた。皎潔嵩高、天下またこれに比すべきものありやと叫んだ。何時迄見てゐても飽くことはない、吾々は又もや立往生をして仕舞つたが、二たび三度人夫に急き立てられて止を得ずこゝを去つた。
更に下ると、間もなく池見橋といふのがある、穗高山麓宮川の池が、此處から見ゆるから名づけたのだといふ。其傍の澤には幅二三間長さ四丁にわたつて雪が殘つてゐる、早速うち碎いて氷砂糖に和して味はつた、これも他に比すべきものゝないと思ふほど美味を感じた。
急轉直下、峠は下つたが、一體に栂の林で道は頗る暗い、大なるシダが繁茂してゐる、駒鳥、時鳥が頻りに啼く、折々は啄木鳥のヶタヽマしい大聲に驚かされる、突然放牧の牛馬に出逢つて魂消ることもある、林の道は馬鹿に長く、日は暮れて來る、雨は降つて來る、具さに困憊を極めたが、林を離れて梓川の橋を渡り、温泉宿の新しい屋根を朧ろに認めた時は、初めて蘇生の思ひがした。
六
上高地温泉株式會社と、嚴めしい標札のかゝつてゐる宿屋は、島々から六里、飛弾の蒲田から三里、ドチラも大きな峠を越さなければ來られない、深山中唯一軒家である。秋は十月から雪が降つて、春は五月過でなければ道が通じない、飛彈越中あたりから信州へ抜る近道で、夏中は一日一人位ひの旅行者もある、山岳會の紹介で、年々槍や穗高への登山者が來て泊るだけで、湯には別に著しい効能もないためか、浴客としてはあまり人は來ぬとの事である。
家には年老いた夫婦者のほか誰も居ない。去年の冬から留守をしてゐた老夫婦は、こゝで悲惨な最後を遂げたといふ。冬は積雪のため交通が絶えて仕舞ふのであるから、食物其他の用意をして冬籠りをしてゐたが、この春、獵師の嘉門次が雪の中を尋ねて往たら、婆さんは病氣で死んでゐて、遺骸は座敷に轉がしてある、爺さんは風邪だといふて、氣息俺々身動きも出來ぬ有樣で寝てゐたので、驚いて直ぐさま島々へ引返し、村人を集め醫者を連れて大困難をして來て見たら、其時には最早爺さんも息を引取つてゐたとの事である。
白木の御神樂堂と評された此の家は、建てゝから間もなく、疊建具も揃つてゐない、疊は此邊に生へてゐる草を乾して作つたものだといふ、雪のためか、柱は狂つて障子のタテつけも惡しく、雨戸は全く動かない。浴漕は三四坪もあらう、深い底まで透いて清しい湯が溢れてゐる、霞澤の山を窓越しに眺めて、湯に身體を漬けてゐる心持は又なくよい。
燈火も明るく、寝道具も惡くはないが、膳の上は我慢が出來ぬ折あしく岩魚も捕れぬといふ、何やら臭い乾した貝、鼻向のならぬ鹽鰤、隨分惡食に馴れた身でも閉口せざるを得ぬ。島々で求めた福神漬もお話にならぬ程まづい、上高地名物とでもいはうか、虎杖の鹽漬で籾混りの飯を無理に嚥こんた。
七
十八日、朝早く起きて、食前に河原へ出て霞澤山を寫した。霧がこめて山は見えたり隠れたりする、朝日は霧を透して、谿も澤も淡いオレンヂ色になり、前景の楊ばかりがハツキリと見える、草には露ふかく、小さな蟲が顔や手にたかつてうるさい。朝飯後、昨日島々から連れて來た人夫を案内者として、宮川の池へゆく、昨夜の道を峠の下迄戻るのである、橋のあたりからの穗高は、徳本峠から見たのとは、また別樣の眺があつて面白い、彼は正面、これは側面、隨てこゝからの方が、波瀾も多く變化も多い、惜むらくは、山があまりに近く吾々の視角のうちに入らないから、繪にして此大なる光景を其儘現はすことが出來ない。頭を南へ向けると燒岳が見える、此の山の男らしき形――それは兜を伏せたやうな――雄々しき輪廓を見たばかりで何とも云へぬ美感が起る。それに加ふるに、此山特有の色の美がある、それは私の好きな例のコバルトグリーンに、僅かにクリムソンレーキを刷つた紫色で、頂上近くに赭岩が見えて、一抹の煙が地を這つて居るのもよい。右を見ても左を見ても、自然は極端の美しさを惜氣もなく現はしてゐる、昨日峠の上りで、この旅行を悔んだが、今日はその反對に、月の此處にある幸福を喜んで感謝した。
林の中には水がある、樹皮は青苔に包まれてゐる、水は透明にして緩やかに流れてゐる、地に一點の穢もなく、水に一塵の泛べるを見ない、實に仙境とはかゝる處を言ふのであらう、峠への道ヘゆかず、左に梓川に沿ふて、たゞ方向を定めて雜艸の中を歩むこと一里、濶き河原に出て、寒流を徒渉した、川の幅は三十間に滿つまい、深さは腿に及ばないが、其冷たき事は意想の外であつた、聞けば此川、秋冬に水なく、春より夏へかけて、山々の雪解の滴りが、この多量の水となるのだといふ。
感覺を失つた脚を擦り擦り、雜木の中を分けてゆくと、又もや幅十四五間程の激流がある。今度は徒渉が出來ない、上へ下へ緩流を求めたが、そのやうな處はない、漸くにして見つけ出せしは、大なる枯木の、橋の如く水に横はつてゐる場處である、枝に縋り幹を傳ひて、注意に注意して川の半ば頃迄往くと、頼める枯木はそこに盡きて、對岸からも同じやうな木が出てゐる、二三尺は水の上を、こちらの木から向ふの木迄飛ばなければならぬ、水は木に堰かれて白く浪たち激してゐて、見るから物悽い、人夫が事もなく越してゆくので、大勇氣を振ひ起して跡に續き、無事に通つたが、若し一人ぐあつたら引返したに違ひない。
間もなく嘉門次の小屋へ來た、老爺は岩魚捕りの名人だそうなが、折柄留守であつた。此小屋の後ろ、根曲竹を分けてゆくと宮川の一の池の畔に出る。
八
池の畔、白石楠花の亂れ咲くあたりに小さな祠がある、前には穗高山上に在つたのを、此處迄下したのだといふ。南安曇郡穗高村に本社があつて、此處はその奥の院である。往昔は、毎年祭日といふと、神官や氏子の者が山上迄參詣に來たのであつたが、いつか山上の社を山下に移した、それでも遠しとして、近頃では奥社參詣と稱して村は出るが、途中で蛇を見たら、其處で參拜の禮を濟ませて引返すやうになつたといふ。この分では今に村外れにはざはざ蛇を放つて置くことになるであらう。
根曲竹に遮られてゐた宮川の池は、社を廻ると直ぐ岸になつて、蒼くして美しき水が忽ち目に入る。周圍にある樹木は小さく、針葉樹乏しく、背景たる穗高はあまりに高くして、繪とするには好位置ではないが、其幽蓬靜寂の趣きは格別で、途中の危險を犯しても、わざわざ來て見る價値は充分ある。
一の池に續いて二の池がある、大さは前に比して其半に及ばぬ池とはいへど其實急流で、水面は平であるが、底に烈しく動いてゐる。苔蒸したる巨岩が水中一面にあつて、名工の手になつた古い庭を見るやうである。寺や邸の、古庭の水石の配置が、あまりにセセコマシク人工的で、甚だ不自然だと思つてゐたが安ぞ知らん、それ等は却て深山の自然を有の儘摸したものであつた。三の池は一層小さい。
此池畔に一枚の寫生を試みんとしたが果さなかつた。此池を見るには、晴れたる日の午前十時といふ時はよくない、曇つた日ならよからう、朝早くもよからう、併し一番よいのは、空に一つ二つの星の見えそめし夕暮の頃ではあるまいか。山の裾は漸く闇に包まれ、僅かに山頂に殘光を仰ぐの時、再び此池畔に立つて、嚴粛にして平靜なる自然の美を、飽く迄味はつて見たいと思つた。
九
危ふき藝當を繰返して、徳本の小屋に出で、こゝに案内者と別れ、溜り水に影を侵せる楊の古本を寫生した。徳本の小屋には、牛馬の番人が居て茶を煮てくれた。(口繪參照)
若き古き、無數の楊の林をわけて、穗高の一角をスケツチしたが、下界とは調子が異つて纒まらない、そのうち又雲が出て來たので、宿の方へ引返す。
橋を渡り、宿近くの笹原から、雪の穗高を寫し始めた。暮れゆく空の感じもよい、麓に立てる枯木の白きもよく調和する、一時間程筆を運んだが、虫の多いには如何ともすることが出來ぬ顔といはす手といはず、少しの隙さへあれは何處からでも螫す目にも見えぬ程の細かき蚋、細く痩せたる刺蝿、茶褐色せる蚊それ等が絶間なく附纒ふて妨げる、手を打振つて追つた位ひでは逃げない、虫に觸れて拂ひ落さねは止まぬ、油斷して整螫れた跡は非常に痒い、此苦痛は容易な事ではない。
宿へ歸つたのは七時半、旅では宅に居るよりも食の進むのが常であるが、今度はソーゆかぬのは不思議である。晝は蚊が居て夜は居ない、山中の宿でも蚤は中々多い。
十
十九日朝も昨日の霞澤を續けた、霧はあるが、空が曇つて感じがまるで違ふ。(口繪參照)
食後、同じ場處で、暗い山麓の一部を寫してゐると、急に雷鳴がして雨が降つて來た、道具の始末もソコソコに宿へ引返して入口の土間から雨の柳を寫生した。磯部氏は橋のほとりでやつてゐたが、傘を持たぬためづぶ濡れになつて歸つて來た。
雨は中々に止まぬので、座敷へ戻つて縁側から背後の山を描いた、雲の去來劇しくして、明るくなり暗くなり、描寫に困難を感じた。幾羽ともなき杜鵑が間斷なしに啼いて、風流どころか頗るうるさい。
島々から人夫が來て、頼んでやつた鷄卵と新聞を持つて來てくれた。鷄卵は一人前三個だけしかない、早速其一個を夕飯の菜にしたが、嘗てこれ程美味な玉子を食べれことがない。
この日甚だ寒く、室内に在ても吐く息が白く見える。夕方から雨は止んだが、例の杜鵑は夜一夜啼き續けた。
十一
二十日は快晴、此日は一筋道を辿つて川下の方へ往つて見た。草木の緑は春の如く柔らかく、其色は淺い。地には名も知らぬさまざまの草花が咲いてゐる、姿愛らしき車百合もちらほら見える。栂の林を越すと落葉松の林がある、シラカンバの林がある、山の裾には、墓場を聯想させる枯木の一群がある、虎杖は人の身の丈けよりも高く茂つてゐる、覺束なき獨木橋架せる小流を幾度か渡りて、砂地現はの平地なせる處に出で、こゝで栂の枯木を前景として穗高を寫した。不相變虫が來るので、今日は武装した、頭から風呂敷を冠り、眼だけ出して顔は不殘包んだ、手には手袋、脚には脚胖、皮虜は少しも露はさぬ樣にした、それでも眼の前にクルクル廻つてウルサイ事は異らない。
毛織のシヤツ二枚、それに夏服、その上に頭から包んで、日向に居て少しも暑いとは思はぬ。海を抜くこと五千余尺の、この上高地の季節は、丁度春であらう。あらゆる植物が、芽を出し花を開き實を結ぶのは、この四五十日間にある。それと同じく、あらゆる蟲類も一時に發生するのであらう。鶯も今こそと耳元近くで啼いてゐる、杜鵑も决して負けてはゐぬ、河鹿も聲を張上げて歌つてゐる、山中でもなかなか靜穩ではない。
磯部氏は午後から上流の方へ往かれた。私一人になつて、更に流に沿ふて、一里ばかり下つて。燒岳の麓近くに至り、楊を中景に置いて、穗高の雪殘を主として寫した。一條の道こそあれ白晝なれど人の姿は見えぬ、絶えず何物にか嚇されてゐるやうで、屡々前後を見廻し、僅かの物の音にも駭ろかされて、オチツイて筆がとれない。併し、位置のよかりし爲め、幸ひに好スケツチを得て、此處を去り、前々日の半成なりし、橋手前の寫生を續け、薄暮宿へ歸つた。
十二
此地、梓川の通する南方僅かに一條の深谷を除いて、三面皆高山である。從つて日出遅く日没早く、空は天窓より望むが如く狹く限られてゐる。日出日没の光景は見るべからず、されば朝と夕とは、たゞ四邊のほの暗く覺ゆるのみにて、空の色は晝の如し。今宵、月明らかに蒼★を照す、而して、この明月の夜空を仰げば、晝と同じく鮮やかなるコバルト色を呈してゐる、これ一には、空氣の透明なるによるのでもあらうが、また他にて見ることの出來ぬ現象と感じた。
二十一日快晴、獨り川下へゆきて二枚の寫生畫を得、暮方より宿近く歸つて、梓川を隔てゝ燒岳を寫した。日は既に西に傾いて、空氣は甚しく黄を含んでゐる。かの雄々しき山の姿は、濃き桔梗色をなして、明るき空に突出てゐる。其前に裾曳く山々は、幾重かの濃淡をなして、前なるは益々暗く、後なるはいよいよ淡い。梢明るき幾十株の楊は、湖の如く波なく音なくして流るゝ梓川に、影を浸して靜まり返つてゐる。水は透明比なく數十尺の底の砂をも數ふべし。脚下の深淵、三四の遊魚の、流に溯つて頻りに進みゆくのが見える。(口繪參照)日は沈みて水蒸氣たち、一度塗りし畫面は容易に乾かず。明日は此地を去らねばならぬ身の、殘念に思へど如何とも爲し難く、箱を閉ぢて宿へ歸るこの夜も月清く山氣冷やかなり。
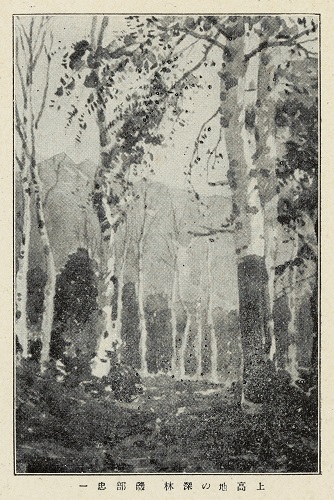
十三
二十二日、いよいよ出立と、たゞ一つ殘つてゐた鷄卵を食し、結束して宿を出でた。荷持の人夫は岡田作次といふて來た時と同人である。心なしにや、今朝は四邊が一層美しく見える、袖引留られるやうで足の運びは遅い。對岸數町かの奥に田代の池があつて、宮川よりも一層悽いときいてゐたが、再遊のおりにと愛を割いた。節は既に土用中である、が風寒く、橋の上には霜が置かれた、七月雪降ることに珍らしくはないといふ。
もと來し道を峠へと急いた。家づとにもと、車百合數株を荷に添へた。峠は前の時に懲りて、今度は歩數を數へつゝ徐々と上つた、池見橋迄苦もなく達したが、其數は四千歩であつた。溪の殘雪はまだ解けぬ。穗高のよく見える處で畫架を裾へた、人夫は枯木を集めて焚火をしてくれる、これで虫の害は免るゝことが出來た。日は高く昇つて山の雲の色は平凡になつたが免に角スケツチに其趣を傳へた。(口繪參照)
岩魚返りの下、溪流の巨岩が面白いとて、そこでも一枚の寫生をして、島々へ着いたのは五時、清水屋に草鞋の紐をといた。
清水屋は山中としてはハイカラの宿屋で、上高地から出て來た身には何でも物珍らしく感じた。風呂は宅になく、此家の持つてゐる湯屋が近くにあるといふので、水下駄引づッて往つて見た。入口で衣類を脱いて、浴室に入ると、薄暗い中に澤山の人が蠢めいてゐる、板一枚の仕切りはあるが、男女混浴で何となく穢なげだ、廣くして清い上高地の温泉につかつて來た身には辛抱が出來ないので、直ぐに飛出して仕舞つた。
湯屋の入口に「櫻もち」といふ行燈が懸つてゐる、どんなものだかと、甘味に飢ゑてゐたので試みて見た、簿い餅に葛餡をかけたもので、滿更ではないが、それを盛る器物の不潔なので、お代りをする氣になれなかつた。
今宵久々で岩魚にも面會し、綿軟かき布團の上に横はつて、快よく夢を結んだ。
十四
二十三日も續いて快晴であつた。朝飯前、梓川の岸へ出て柳を寫す。水は乗鞍の麓より出る石灰のために、白濁して感じは惡いが、沿岸の景色は捨たものではない、裕に一週間位ひの材料はあらう。十一時に、波多官林の手前、柳の大樹の前に來るやうにと馬車屋と約束して、吾々は早くよりそこヘゆきて、老楊のスタデーをした。此木。幹の太さ幾抱へ、枝は四方に蟠りて、數百坪の地を影にしてゐる。木振枝振、稀に見る面白き姿で、この木一本のため態々寫生に來てもよい程である。
十一時を過ぎ十二時になつても馬車は來ない、詮方なくて歩行を始めた。晝食をするにもそのやうな家がない、漸く一軒旅店を探し出したが、飯の仕度は出來ぬといふので、生玉子を買つて飢を凌いだ。波多の松林を過ると出口に馬車屋がある、幸、今松本へ向つて出る處だといふので直ちに飛乗つた。駒の進みの早くして、鞭の音稀に、來た時の樣に心を痛むることはなかつた。
四時松本へ着いた、公園の寫眞師を訪ふて、穗高山の寫眞を求め、五時發篠の井行の列車に投じた。
十五
偶然にも、同じ客車に未醒君が居た、木曾の御嶽へ登りて、是から長野へ向ふのだといふ。車は犀川を左にして進む。田澤、明科あたりに風景頓に雄大に、遠く日本アルブスの連峯が、峭壁のごとく峙つてゐて、安曇の平原前に展け、半里にあまる川幅を有する犀川は、眼前に横はつてゐる。折から、日は沈まんとして、連峰の輪廓いよいよ鮮やかに、空を寫せる水は益々明るく、この時天地が急に廣くなつたやうな心地がした。
空の暗くなるに連れて、月は光を増し、幾つかのトンネルを過ぎて、車の姨捨にかゝりし頃は、月光晝の如くであつた。田毎の月の名所は此處か、杳かに千曲の流れの、幾筋か白く光れるのが見えて、農家の燈火、点々其間に閃めいてゐる。やがて篠の井に車は止まりて、待つこと一時間、長野より來れる上り列車の客となつて、半ば眠りつゝ、無事上野に着せしは二十四日の曉であつた。(明治四十年夏)
(諏訪の宿料は壹圓程○荷持人夫は一日壹圓、人夫の返りの 日當迄拂ふこと故一回貮圓になる、但食料は人夫自辨○上高 地の宿料辨當付一日五十錢○島々の宿料一泊六十錢。
