私に畫が描けたらば(二)
礒萍水
『みづゑ』第八十九
明治45年7月3日
この月も私は畫が描けたらばの噺を續けます、然し私は、ただ單に、自分が畫にしたかつたと謂ふ其場合をのみ、思ひ出の儘に並べたてるのでは有りません、私が斯う謂ふ問題を提供したのは、一の目的があつての事です、それはこの談の結果に於て解し得られます。
『山岳家の見たる山の色』を話しませう。然しこれは甚だ難かしいのです、何故と謂ふのに、その色は私が一人感得したのみでして、詞をもっても、文章をもつても、迚もその儘に謂ひ現はせる筈のものでは無いのであります。
三月の十日でした、私の先輩のK君は、一寸した用事で私を尋ねて見えられました、玄關での立話、いづれまたと歸りを急がれました、私は餘りの不意打と、何とも謂ひやうもない失禮をしたやうな氣がして、その儘お別れするのが罪惡のやうに思はれて成りませんでしたので、帽も冠らず、その儘突かけ下駄で外に送りに出ながら、K君の家は山一とつ越えて行かれるので、私は話しながらつひぶらぶらと行きました。
胸をつくやうな急な坂を登りきると、だらだらと小路が蛇のやうに迂練つて居ます、それを傳ひながら行く、私の領分の山は盡きて、ここからはだらだらの下りになる、私とK君とは並んで歩いて居ました。
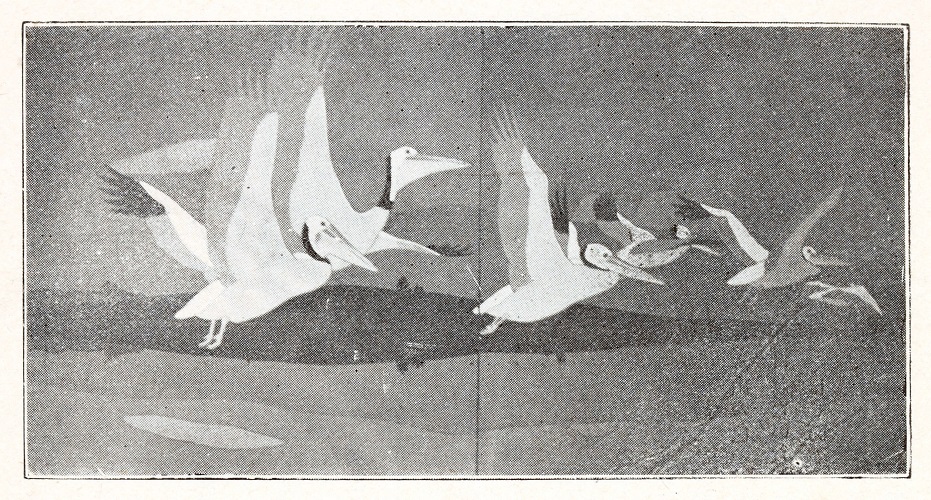
晴れた春の日の、沒るにはまだ一時間も間がありましたらうか、『ああ今日は好く見える』
K君はさも嬉しさうに謂はれました。
谷戸を三つほど越してその先の丘の上に、新らしく建てられた小學校の校舎の上に、山が浮いて見えます。私はK君の聲に初めてそれを仰いで見ました、何の山でしたらう、恐らくは足抦續きのそれでしたらうか、または彼の山北から入る丹澤山の一端でしたらうか、實はその時私には、それが何であるかを訊くの勇氣もなかつたのでした。私は山の話と來たらば全部門外漢なのですもの、何で此の山博士と太刀討ができませう。
『ああ好く見えますね、これは綺麗だ』
全く綺麗だつたのでした、山の人の前でのお世詞では無かつたのでした。然しそれは一時の暗示に刺撃されての、一種の迷景的の美に襲はれたのでした。
如何に山らしい山に登つた事のない私でも、山の色はよく解ります、ですのに此時の山の色はどう謂ふものでしたらう。
私は畫の具の合せやうを知りませんから、それを畫具で説明は能きませんが、濃い淺黄の、冴えた、冴えた、表面に艷やかな光澤のある、私が日頃見なれて居る山の色の、超然的の色とは全で違ひました。何とも謂ふに謂はれないなつかし味のある色をもつて居たではありませんか、そして而も、校舎の家根の上に浮き出して、手でもその顏が撫でられるやうに、近づくとその呼吸の香りもえるばかりに見えたのでした。實際私にはさう見えたのでした。
私は、その時は、敢て不思議とも思はなかつたのでした。ただ美しい山の色とばかり、その原因を考へても見なかつたのでした。
お別れしてから、歸りは一人で、また舊の途を歸つて來ました私は再ぴ先刻山を見た所で、もう一度山を見て見ました。
ものの十分とは經つて居なかつたのでしたが、山の色は暗い淺黄、と謂はうよりただ暗い、ありきたりの山の色ではありませんか、日は未だ春かないのですから、勿論光線の烈しい變化はありません、それだのに、何故でせう、山の色は先刻、K君に謂はれて見た時のやうに、ちかぢかと、色鮮かなものではありません、暗く、陰氣に、人なつかしくない、結局私が日頃見つけて居る平凡な色になつて居たではありませんか、私ははつと思ひました、私は成程と手をうちました。
私はK君に暗示の色を授けられたのだ。私が常からK君を山の神樣のやうに思つて居たのでK君に山の色を敎えられて、さてその時に見た山の色は、あのやうに美しくも、人懷かしくも見えたのは、あれは吾々の見る山の色では無いのだ。吾々には彼のやうに、山を美しく、懷かしく見るの權力はもつて居ないのだ。あれはK君が見る事のできる色なのだ。私はK君の力量に感化されて、その一刹那に於て一瞬の美と山の情けを味はふ事が能きたのだ。
私は喜びました。計らずも山の眞實の色彩を見る事が能きましたのを喜びました。
題して『山岳家の見たる山の色』としませう、然し圖なんかはどうでも宜しいのです、森の邊に山が出やうと、河原の當面に山が聳えやうと、かまひません、單に山ばかり描いても差支へは有りません、要は山の色彩を現はすのにあるのですから、然し私は困ります、私の感得した『山の色』は、私の瞳の底に泌み込んで居るのでして、それを斯うと説明する事が能きないのです、それにしても忘れられないのは彼の時の山の色であります、私は自家の誇として此『山の色』を深く珍藏します。『水郷の魔火』と假り題を置きました。此の材料をもつて此篇の結局とします、これは潮來の夜の色を描くのです。
舟に置炬燵があつたのが、先づ私には謂はれない程の嬉しさでした。十二月の中旬すぎ、風が巨魔の嘯きのやうに、間をおいては凄まじく吹き捲ります、それに面を向けては呼吸もつまる程でした、そして寒い事、寒い事、この儘氷り付いて了ふのかと、正直思はずには居られませんでした。その場合、この木枯の吹き荒む水の邊を渡るの夜に、私にはこの炬燵がどんなにか嬉しかつたでせう、私は外套の釦を殘らずかけて、襟を立ててただもう意氣地なく炬燵にしがみ付いて居ました。

風が枯芦の邊を吹き渡つて行きます、ざわざわと氣味惡い音を立てます、あの怪談にきく障子に觸る髪の毛の音と謂ふのは、斯うした音なのであらう、櫓のきしりが、ぎいぎい、ただそれぎりでず、私の天地の間の音と謂ふのは此の二つぎりでした、私は心底から寂しさを悲しまずには居られませんでした。
船頭は老人で、而も耳が遠いのでした、何を話しても一度や二度では通じません、迚も埒のあくのでは無いのでした、私は會話も諦めて、船宿から寒さしのぎにと乗せてくれた酒を、ちびりちびりと、飮めもしませんのに、實際寒さをしのぎたい計りに甞めて居りました。
なかなか潮來に舟は着いてくれない、最初の中はまだかまだかと心を焦だちましたが、いくら待つても舟は着かうとはしません遂に我を折って、どうとでもなれ、勝手にしろ、一夜中この舟の裡に寢たとて死にもしまいと、失望から樂天になつて、醉つて倒れた方が益だと、自暴と二人連れで頻に盃に親しみました。
盃に月が姿を寫します、風がそれを吹き散します、
と突然に、盃が暗くなりました、おやと思ふ間に、また明るくなつて、明るく成つたと思ふと、また忽ち暗くなる。
漸やくの事で私にはその原因が解りました。橋の影です、私の舟が橋の下を通る度に、橋の影が盃にさすので、盃が暗くなる私は非常に詩趣ある事に思ひました。
潮來出島は四十八橋、そんな事ではありません、百橋にも餘りませうか、その橋と謂ふのが、獨木橋のやうなもあれば、淺橋程のもある。その面白さに私は、酒は飮まずに、盃についだ儘、ただ盃中に寫る橋の影、明暗面の白さを見惚れて居ました。吹きつけられるやうに私は、呼ぶやうな唄ふ聲と、天邊から降つて來たやうな太鼓の音とを聽きました、吃驚しました、今までが餘り寂しすぎたのに、思ひもかけずこの調子の狂はしい音樂をきかされたので、一種の恐怖を感ぜずには居られませんでした。
風に乘つては、高く、低く、遠く、近く、續いては、絶えて、如何しても魔の樂聲です、私は首を龜めながら四方を眺めましな。
舟は一角を折れて、つと川幅の廣い水路に入りました。
私の仰いだ眼に見えたのは何でありましたらうか。
月に隈をとられて輪廓がくつきりと、浮び出たやうに明瞭に二階立の家が四五軒、灯が黄色に鈍くとぼつて、煤けた障子のどれもは立てきつてある、叫ぶやうな唄と狂はしい太鼓の響きはそれから洩れたのでした。
その時の家の黑い黑い色、凄じいばかりに黑い色、月によつて區劃された輪廓の美しさ、就中私が胸に應えたのはその灯の色でした、煤けた障子の裡の灯火の色、何とも謂ふに謂はれない、鈍い、そして底に魔の潜むらしい色、私の描いて見たいと謂ふのはこれです、この灯火の色です、私が何を描かうとして居るかは大略お解りに成つたらうと思ひます、暮れ行く山の中の一路、同じ色で塗られて殆んど識別に苦しむ程の線、それは人外魔境への途なのです、山岳を愛好する人の見た山の色、それは百册の書を讀んでも知る事の能きない山岳家獨有の色、死のやうな寂莫から誘ひこまれて見せられた魔界の黄な灯火、私はただただ其刹那が描きたいのです。その一瞬に感じ得た色彩をその儘畫に現はしたいのです、私は氣分を尊びます、氣分の畫が欲しいのです、ただ圖の携へや色がすく塗つてあるのは望みではありません、畫を通して筆者その時のムードが觀る者の胸に應えさへすれば私は滿足します。
私に畫が描けたらば、私は終末に至って此自問を自答します、私は氣分の畫が描きたいのです。
