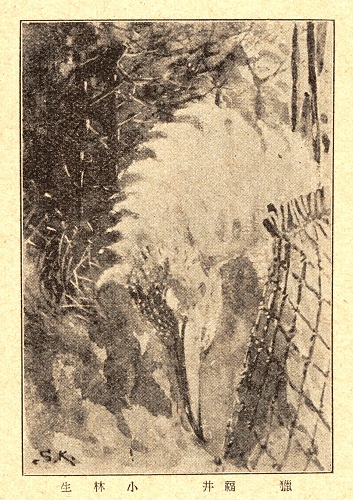僕の動機
内藤六丁
『みづゑ』第十一 P.20
明治39年4月18日
僕が始て水彩畫に志したは餘程以前の事で、甚覺束ないが記臆を辿て書て見やう、明治廿何年であつたか上野に第何回内國勸業博覽會(?)があつた時、淺井忠先生の油畫を見たのが抑の動機であつたやうに信ずる、其時の先生の出品はタイシタもので、大幀長幅ばかり凡三十點もあつたやうに思ふ、肖像も靜物畫も一二點はあつたかも知らぬが、大抵は僕がすきな景色畫て非常に愉快に感じた、其中で最も僕の眼を惹きつけたのは慥『寒驛霜晴』と題したのであつた、僕は其の畫の前に何でも四十分間ばかり引付けられて居たであらう、今でも眼を閉ぢて居れば其畫が判然と見えるのである、爰で其畫を説明するのは傍題の嫌はあるが少し容赦を乞ふて書て見る、畫面の中央よりは稍左に寄た方に、大道が緩き勾配にうねつて、其の左方は樹木と垣などで家は無かたやうに覺える、右方は古き町家で間マ二階家がある、其二階の前の庇には蒲團や、干大根や小兒の襁褓やうな物が譯も無く干してある、其が古き家根とよく調和して零落した驛の樣がいかにも遺憾なく現はされてゐる、其街道の中程に二三人取卷て焚火をしてゐる、そうして其烟が眞直に鮮な空へ立昇てゆく樣などより、其れがドーしても掃き寄せた塵、木の葉などを燃やして、霜凪の靜な朝に暖をとりつゝ語つて居るやうに見えるのでむる、僕の眼に映じて居るのは此れだけで、其の前景背景は何であつたかは一向に記臆して居らぬ其時僕はかう思った、西洋畫と云ふものは斯云ふ處までかけるのか如何にも自然に迫つたる藝術である、羨しいことである、併し殘念なことには技術は云ふ迄もないが、繪の具や其他の道具だてから見ても僕のごとき素人の一寸眞似も出來そうにもない事だ、斯云ふ藝術を早くから修めなかつたのが、今さら詮もないことだが僕が終生の不幸だ、と遂には嘆息の氣味で其室を出て仕舞つた、(尤も其以前に本多錦吉郎先生などの油繪を見たことはあつたが、其れは金碧燦爛たる日光の陽明門や着色寫眞のやうな肖像畫であつたので、僕の美感を挑發するに足らなかつたのである)さて、そうあきらめたやうなものゝ、其後は兎角其れに心が引かされて、旅行などした時、ある景に出遇ふと自分が淺井先生のやうな手腕を以て、精一抔に其景色を寫して見たいものだが素養のないのは返す返すも殘念なことだと、折角其處まで書て來た紀行文もそれがために頓挫して、中止するやうなこともあつた、兎に角正式にかくことは出來ぬ迄も、描くだけの方法や準備だけでも詳く聞て見たいとは、其頃始終思て居た處たか、田舍に居る悲さには其れさへも機會がなくて仕舞た、其後何年であつたか上野の五號館の展覽會で確と記臆せぬが、可なり澤山な西洋畫の陳列があつた時、初めて三宅先生の水彩畫といふ物を觀たのである、其時三宅先生の作品ばかりも、卅四五點あつた、其が然も悉く水彩畫で、其他の諸先生のは又悉く油畫であつた、三宅先生の作品で淺井先生の其れの如く、今でも記臆してゐるのが『朝霧』と云ふ題で、快くおひ茂て居る樹間に、一小池があつて其池邊に何か洗物をしてゐる點景人物があつた、夫が總て稍青みがゝつた薄き幕に包まれてゐる圖で、至極簡單な小扁ではあつたが、題意が非常に能く表はれで居た樣に思つた其他の水彩畫も皆其々愉快に見て廻つた、要するに總體を通じて、僕は此時一種の新らしき快感に打たれた、`其れは此れ迄油畫を見た時には曾て起られなかつた一種の美感である、強て云へば『清新』とか『洒脱』とか形容すべきものであつた、其處で不思議なことには此等の水彩畫を見てから、右方の室の油畫を見て廻つた時に水彩畫を見るやうな愉快を感ぜなかつた事である、勿論『豪放』とか其の反對の『精巧』とか云ふ方面は慥に認められるが、僕がすきな『清新』といふ感は、ドノ油繪を見ても起らないばかりでなく油繪全體を通じで或る陰欝な氣が何處かに存じて居ることも認めたのである、其處で僕は又引返して再三水彩畫の方を見たがドーしても愉快でたまらぬ、すると忽ち斯ふ疑向か起た、油水兩畫に就て僕の今認めた感じは先づは誤がないやうに確信する、大抵な人は屹度僕と似寄た感じを起すに相違ない、果して然らばだ、ナゼ洋畫家は油繪の外に大にドシドシ水彩畫をやらぬだらう、三宅先生の外には此丈け見える諸先生の顔觸で誰一人水彩畫を出した人がない、なぜだらう、油繪よりは水彩畫の方が六ヶ敷いかしらん、六ケ敷にしても多士濟々洋畫會中、水彩畫をかく人が他にないとは大に合點のゆかぬ事である、して見れば水彩畫なるものは、僕等の如き赤素人の眼からはよく見えても、大家專門の人より見れば存外淺薄なもので、美術として賞に鑒値する程の物でないとか何とか云ふのではあるまいか、イヤそんな譯は斷じてない、何程高尚な藝術品でも公衆の鑒識を相手にせぬものはあるまい、僕がごときものゝ眼から見ても其美を認めらるゝ物は、必す亦多衆の眼にも美と映するに相違ない、其れを他の諸先生が顧みない風をして一枚も描て出さぬのが益恠しからんと、こゝまで推詰た處で、フト最後の斷定に達した、それは水彩畫について僕の見た處に間違はない、又諸先生においても慥にそう認めてゐる、けれども、描て出した處で、水彩畫の外何にもかゝぬ三宅先生の其れには今の處到底及ばない、其故に出品せぬのであらう、と云ふのである、先づ此の推測が一番事實に近からうと自分できめて置て、偖つくづく水彩畫を見ると、繪の具も名の如く水繪の具らしく、地も紙で只の西洋紙の稍厚いの位のものゝやうだ、其れで畫面も油繪よりは概して小さくて足るやうで、比較上何にかに輕便で面倒な準備なども入りそうにもない、こゝから見ると水彩畫は素人にも一寸貌似が出來そうだと思はれた、サアそう思つて見た日になつて見ると、矢も楯もたまらなくなつて、直ぐにも描て見たくなつた、取敢へずドレか一枚手本として買て歸らうとまでは思つたが、一小額面に其頃大枚五六圓といふ金を支拂ふことの其れが僕の懷の勘定よりは、寧ろ何だか世間態がおかしいやうな氣がして、殘り惜かつたが終に買はずに宿へ歸つた、其の翌日は先第一に材料の仕入といふので、本郷から神田、それから京橋まで西洋の筆墨紙を賣るやうな店こ見れば、殘らず「西洋水彩畫といふ繪をかく紙と繪の具はありませんかナー」といふ調子で聞て歩いたが何處にも無かつた、其の翌日も方面をかへて尋ね廻つたが一軒も當り付かなんだ、今度は手段をかへて知己訪問と出掛て、四人ばかりに尋ねたが皆門違のことゝて一向知れない、仕方がないので其の方は一先づ置きにして、其れよりは何か水彩畫のことを書た書物を買て、其れを勉強して居るうちには他の事情も分るだらうと云ふ、無據い漸進主義を取つて、丸善へ出掛て買たのが「レイチ」とか云ふ人の横本の水彩畫帖であつた、歸り掛に店の番頭に繪の具の事を聞くと、佛製の餘りよくない物だが有るといふ、其時は丸善は何だか矢鱈エライやうな氣がして嬉しかつた、其の書物と繪具箱を持て其翌日直に歸國した、其れから一ケ月も其の本を研究して、そうして粗末な畫學紙を買てお手本通り臨本摸寫もやれば實物寫生もはじめた、根氣よく四月の間、隙があれば夜晝なく續けたがドーしても物にはならなかつた、殊に色の調子において重に失敗するのである、自分ながら無器用なのに愛相が盡きて、果ては僕は先天から畫を描く資格を持て生れなかつたと迄思詰めたのである、併し未練は殘てゐる、一昨々年出京した時三宅先生の東京近郊を畫た最初の『スケッチ』と云ふ物が初めて手に入つて、其を見ると今迄困難を感じた點について發明した處が出來たやうに思つて、歸りには小山驛で汽車を下りて其れから徒歩で足柄山中竹の下、金時山御殿場の富士溪上の水車、など凡十枚ばかり二日掛りで寫生して沼津まで出た事があつた、此時の寫生は前に懲りて鉛筆畫の上に薄く水彩を塗た位の事ので、僕が常に理想する水彩畫といふ物には全然ならないので、矢張り不愉快で日を送て居た、すると一昨年の春の頃大下先生の水彩畫の栞に接するの榮を得て、多年模稜の間に在つた事柄が明瞭になつて、どうやら杖なしでも歩けそうになつたので、其れから新に紙も買へば繪具も買ひ、其他の材料も買調へ、改めて水彩畫の領地へ踏出すことになつた、即此時を以て僕が水彩畫をはじめた紀元とするのである、